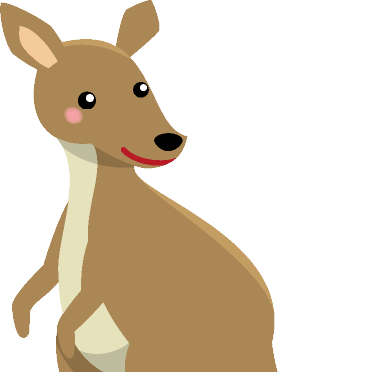はじめに
一級建築士のすごさって、実際どのくらい?
そんな疑問を抱いたことはありませんか?
一級建築士は「建築のプロフェッショナル」として広く知られていますが、試験や資格の実態を詳しく知る人は意外と少ないものです。
本記事では、一級建築士のすごさの正体、過酷な試験の難易度、そして気になる年収事情まで、わかりやすく解説します。
\建築士に関するその他の記事はこちら/
-

-
リクルートエージェント面談 どんな感じ?一級建築士の体験談を紹介
2025/3/12 転職
一級建築士のすごさとは?

受験資格が必要!指定学科の卒業が前提
一級建築士は「誰でも受験できる」資格ではありません。
主な受験資格は以下の通りです。
- 建築学科など指定学科の卒業
- 所定の実務経験(※令和2年度から受験資格としては緩和)
詳しくは公益財団法人建築技術教育普及センターのHPをご参照ください。
つまり、建築を学び、現場経験を積んだ人だけが受験・資格取得ができるという構造になっています。
合格率わずか10%!狭き門の国家資格
一級建築士試験は、以下の2段階で実施されます。
- 一次試験(学科):合格率 約20%
- 二次試験(設計製図):合格率 約50%
- 総合合格率:約10%前後
数字からもわかるように、建築を学んだ人なら誰でも受かるわけではない難関資格です。
超広範囲×長時間の学科試験
一次試験(学科)は以下の5科目で構成されています。
| 科目 | 問題数 | 試験時間 | |
|---|---|---|---|
| 学科I(計画) | 建築計画、建築積算等 | 20問 | 2時間 |
| 学科II(環境・設備) | 環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)等 | 20問 | |
| 学科III(法規) | 建築法規等 | 30問 | 1時間45分 |
| 学科IV(構造) | 構造力学、建築一般構造、建築材料等 | 30問 | 2時間45分 |
| 学科V(施工) | 建築施工等 | 25問 |
出題数は合計125問、試験時間は合計6時間半に及びます。
建築業界全体の知識を問う内容となっており、実務では身につかない内容まで問われるのが特徴です。
設計製図は実技勝負!休憩なしの6時間半
二次試験では、与えられた条件に基づき、
- 設計図面(平面図・断面図など)
- 設計主旨(文章による設計意図の説明)
を6時間半ノンストップで作成します。
正解が一つに決まっているわけではなく、創造力・論理性・正確性のすべてが求められる過酷な試験です。
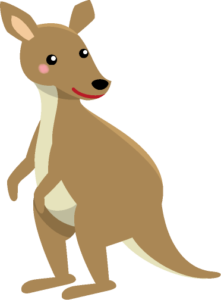
6時間半という長時間、ずっと時間と戦いながら集中するなんて、今までにない経験でした。
大学の二次試験でも長くて150分です。
体調管理も大事になってきます。
実務では身につかない知識まで網羅
建築の実務は専門性が高く、
- 設計だけ
- 構造だけ
- 設備だけ
などに分業されているのが一般的です。
一方で一級建築士試験では、分野を超えた総合力と知識の網羅性が問われるため、実務だけではカバーしきれない勉強が必要になります。
設備設計については下記の記事で詳しく解説しています。
-

-
設備設計の仕事とは?具体的な仕事内容を解説
2025/1/17 建築設備士
-

-
仕事の魅力を伝えよう!設備設計を理解してもらうコツ|場面別5選
2025/1/17 建築設備士
姉歯事件後に試験難易度が上昇
2005年に発覚した「構造計算書偽装事件(通称:姉歯事件)」をきっかけに、建築士の責任と試験制度の見直しが行われました。
その結果、試験の難易度は引き上げられ、より高度な倫理観・幅の広い技術力が求められる資格となりました。
社会人には過酷すぎる試験スケジュール
残業+試験勉強=体力・気力との戦い
建設業界では残業が多いケースも多く、働きながら試験勉強をすること自体がハードです。
- 平日は仕事後に夜間学習
- 休日は模試・演習・通し練習
- 体力・気力・集中力のすべてが必要
まさに、社会人にとって最難関レベルの勉強環境です。
令和2年度から大学卒業直後の受験も可能に
制度改正により、2020年度からは大学卒業後すぐの受験も可能になりました。
とはいえ、仕事をしながら受験する社会人も多く、依然としてその難しさに変わりはありません。
一級建築士の年収はどれくらい?
資格だけでは稼げない?年収を左右する要素
一級建築士は「取っただけで年収が跳ね上がる資格」とは限りません。
年収に影響する要素は以下の通りです。
- 実務経験・スキル
- 所属企業(ゼネコン・設計事務所など)
- センス・提案力・営業力(特に自営業)
- クライアントとの関係構築
ただし、一級建築士を取得していること自体が、一定の信頼・努力・知識を証明する肩書きであり、転職市場での評価は非常に高いです。
\建築士の転職に関するその他の記事はこちら/
-

-
設備設計士の転職完全ガイド|年収アップ&理想の働き方を実現する方法
2025/3/12 転職
-

-
最初に登録するなら【リクルートエージェント】!設備設計者におすすめな3つの理由
2025/3/12 転職
-

-
リクルートエージェント面談 どんな感じ?一級建築士の体験談を紹介
2025/3/12 転職
求人では年収500~1000万円が目安
実際に求人情報を見てみると、一級建築士を要件とする職種は年収500〜1000万円前後で募集されているケースが多いです。
職場によって、年収の幅も異なります。
まず、アトリエ系やデザイン重視の設計事務所は、自由度や創造性が高い反面、年収水準は比較的低めです。
次に、地域密着型の個人事務所や地方設計事務所は、案件の規模や予算により、年収は中間程度となる傾向があります。
大手の組織設計事務所に勤務する場合、業務の専門性が高く、福利厚生や給与体系も整っているため、比較的高収入が期待できます。
さらに、ゼネコン(総合建設会社)の設計部門や現場管理職として働く場合は、プロジェクトの規模や責任範囲が大きく、建築士の中でも最も高水準の年収を得るケースもあります。
\建築士としてどのような環境で働きたいか、考えるのにおすすめの本はこちら/
※はじめての Audible なら 30日間の無料体験 を利用して、この本を読めます
一級建築士試験の難易度とは?

学科は知識量勝負!合格基準もシビア
- 出題範囲が広く、記憶力と理解力の両方が必要
- 各科目に基準点があり、1科目でも落とすと不合格
- 暗記・計算・法令など、学習内容のバランスも重要
設計製図は努力と戦略がモノを言う
製図試験は、課題発表から試験日まで約2か月半しか準備期間がありません。
その間にやるべきことは山ほどあります。
- 想定される課題パターンでの演習
- 表現・構成・文章力の向上
- 試験時間内に描き切る練習(6時間半)
反復練習必須!センスだけでは通用しない
製図には多少のセンスも必要ですが、それ以上に反復練習による基礎力の積み上げが重要です。
- 「素振り」のような反復練習
- スピード・精度・思考の瞬発力を鍛える
- 客観的フィードバックをくれる講師の存在も大切
命取りになるミスも!製図は一発勝負
製図試験では、以下のような致命的ミスがあると即不合格になる可能性があります。
- 上下階の柱の位置が不整合
- 避難経路の不備
- 面積・採光条件の不満足
一つのミスが全体を台無しにする、シビアな設計審査です。
何年もかけて合格する人が多い
一発合格できる人はごく少数で、複数年かけて合格を目指す人が大多数です。
- 学科と製図を別の年にクリア
- 予備校通学・模試受験・製図道具代などで出費も多い
- 仕事との両立で生活は激務に
また、資格の難易度を「偏差値」で表すならば、地域トップの高校合格、または地方国立大学レベルとされることもあります。
しかし実際には、偏差値以上に「社会人として勉強を続ける精神力」が試されるのです。
学歴が高い地頭がいい人でも、努力が必須です。
高校・大学の受験勉強は、まわりも同じく頑張っていたし、受験に向けて部活は引退したため勉強に集中できた。
社会人になれば、休日に遊ぶ人も多い中で、自分は一人で机に向かい続ける——。
そのような環境下で、自分に打ち克つメンタルが求められます。
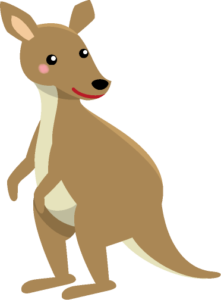
一番印象に残っているのは、製図試験がまるでスポーツのようだったということです。
大学に4年通い、その後も勉強を続けてやっと学科に合格し、ようやく製図の土俵に立てる。
そこからは、基礎を体に叩き込むような反復練習の毎日でした。
もちろんセンスも大事ですが、本番の土壇場で支えてくれるのは、やはり努力の積み重ね。
年に一度の大舞台、一つのミスが命取りになる緊張感は、今でも忘れられません。
おわりに|一級建築士のすごさは、資格以上の価値がある

一級建築士のすごさは、単に難しい試験に合格することだけではありません。
その過程で得られる知識、経験、そして「やり抜く力」は、建築の世界で働くうえでかけがえのない財産になります。
社会人として働きながら、限られた時間の中で勉強を続け、何年もかけて合格を目指す人も少なくありません。
決して楽な道ではありませんが、それだけに合格したときの達成感や信頼は、何物にも代えがたい価値となります。
そして一級建築士は、将来のキャリアや働き方の選択肢を広げ、自分自身の可能性を証明する資格でもあります。
これから挑戦する方にとって、本記事が少しでも勇気と参考になる情報となれば幸いです。
参考記事
-

-
設備設計一級建築士の試験難易度とは?資格取得のハードルと他資格との違い
2025/3/21
-

-
設備設計の仕事とは?具体的な仕事内容を解説
2025/1/17 建築設備士