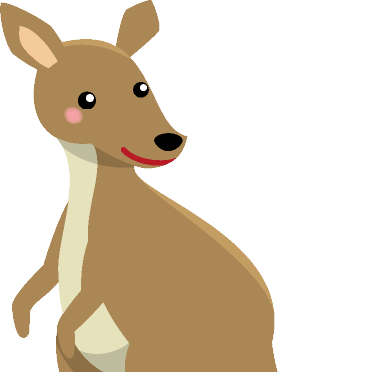はじめに
設備設計一級建築士試験は、設備設計の専門知識を問う高度な試験であり、合格するには過去問の徹底的な分析と理解が不可欠です。
本記事では、【令和6年度空調・換気設備】の過去問を詳しく解説し、解答のポイントや関連知識を整理しました。
過去問を効率的に学ぶことで、試験本番でも応用できる知識を身につけることができます。合格を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
試験の概要などについてはこちらの記事も参考にしてください
-

-
【設備設計一級建築士試験の概要と対策】
2025/2/26
-

-
設備設計一級建築士 試験対策で必要なもの5選【おすすめアイテム】
2025/2/17
空調・換気設備 過去問解説
問1 排煙設備
自然排煙口に関する問題です
法規を順次チェックしていきます
排煙口面積:防排煙区画床面積の1/50以上
1階150/50=3m2以上
2階(150+150)/50=6m2以上
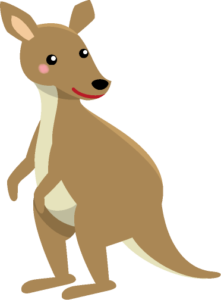
火事の時の煙は高温となっており、上部にいきます
吹き抜け部の煙は2階天井に滞留するので、2階の床面積に含めるのがポイント
天井または天井からの設置距離:80cm以内および防煙垂れ壁の背丈以内
1,2階とも天井から排煙口下端が600≦800、防煙垂れ壁より上部
手動開放装置の位置:一の防煙区画ごと
それぞれ設置されているが、1階吹き抜け部から上階の排煙口用の手動開放装置がない
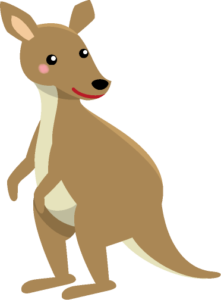
手動開放装置は設置高さが正しいかに目が行きがちですが、必要な箇所に設置されているかもチェックのポイントとなります
手動操作部を壁に設置:床面から80cm以上1.5m以下の高さ
手動開放装置の上端が床面から1200
問2 冷却塔設備
地上15階建ての屋上に設置→11以上であるため、構造が令第129条の2の6及び昭和40年建設省告示第3411号で定められている。
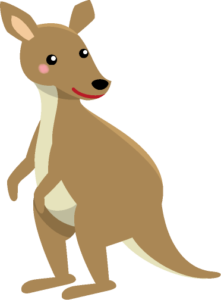
地上何階建てかの条件は見落としがちですが、11階未満の場合はこの告示が該当しないので、注意
充填剤、ケーシング、その他の主要な部分の材質が設問の内容で、容量も3,400kw以下、かつ網目の大きさも26mm以下
冷却塔からほかの冷却塔までの間は2m以上→1.8m≦2.0mのため、不適切
なお、冷却塔Bから屋内までは2.8m、窓がある場合は3m以上必要であるが、ないためOK
問3 煙突
煙突はいくつかパターンがあるためどれに該当するかまずチェック
今回はフードがついているのでフードⅠかⅡに該当するか確認
排気フードから火源までの垂直距離が900→1m以下なのでフードに該当
火源のから(1/2)H(H:高さ)以上水平方向にフードの幅はない→今回はフードⅠに該当
火気使用室に設ける換気設備の構造基準より、給気口、排気筒の有効断面積AV3を確認
設問の図より、給気口は0.09㎡ < 0.0936 給気口の面積が不足しているので不適切
設問の図より、排気筒は内径350φ→0.0961㎡ ≧ 0.0936 排気筒有効断面積は適切
給気口高さは天井高さは1/2以下→天井高さ2500で、上端1200のため、適切
問4 排煙設備
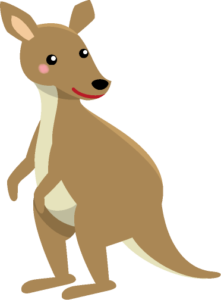
排煙の風量確認問題は頻出、かつ間違いを見つけやすいので確実におさえておきましょう
例えば1階だと店舗A~合流点aまでは、店舗Aの床面積400に対して、ダクト風量が400㎥/minなのでOK
合流点aから合流点bまでは、店舗AとB(隣接する2区画)の合計550でOK
合流点b~cまでは、店舗AとBまたはC(隣接する2区画)の合計550でOK
この設問、このように1,2,3階と順番にみていくと問題ないように見えます
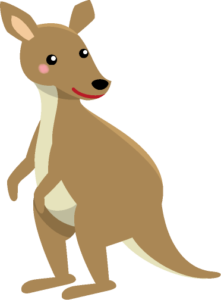
問1でもありましたが、エントランスホールは吹き抜けとなっているので、合流点eまでがラウンジ部分と合算した数値となっているか確認
ラウンジから合流点eまではエントランスホールの150とラウンジの400の合算値、550となっていますね
次に、ダクトスペース内の風量をみていきましょう
合流点c~dでは、1階と2階のうち大きい風量である850で一見よさそうですが・・・
エントランスホールと店舗A(同一フロア)の排煙口が同時開放となった場合はどうでしょう
エントランスホールとラウンジの区画550と、店舗Aの400の合算値がダクト風量となるので、950となります
合流点cから排煙機手前までのダクト風量が850→950必要
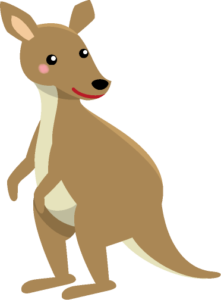
ダクトスペース内の竪ダクトは、このように広い目線で一度立ち止まって考えてみる必要がある場合があります
問5 不適切なものの指示
A:令第126条の2第1項ただし書きより、排煙設備の設置が免除される部分があります
学校・体育館などが該当するため、中学校の体育館では排煙設備なしでもOK
B:外気に常時開放された開口部などの換気上有効な面積の合計は、床面積に対し15/10,000以上
→60㎡=600,000c㎡
600,000×15/10,000=900c㎡ ≦800c㎡→不適切
C:ボイラーの煙突高さは、燃料によって地盤面からの必要高さは異なる
ガス炊きボイラーの場合、9m以上、設問では10mなのでOK
D:ふすま、障子などで仕切られた2室は、法第28条第4項より、1室とみなして換気設備を計画できます
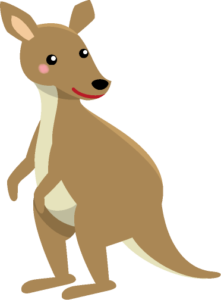
講習テキストにも記載がありますが、この際覚えておきましょう
おわりに
【令和4年度空調・換気設備】の過去問を解説しましたが、いかがでしたか?
過去問を繰り返し解くことで、法適合確認に必要な知識が確実に身につきます。
本ブログでは、他の過去問解説や設備設計一級建築士試験の対策情報も発信していますので、ぜひチェックしてください!
合格に向けて、一緒に頑張りましょう。
関連記事
過去問の出題傾向を把握するにはこちらをチェック