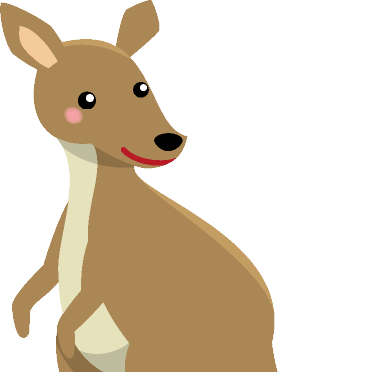はじめに
世界を舞台に活躍する建築家・隈研吾(くま けんご)氏。
その作品は、木や石、紙といった自然素材を巧みに生かし、光や風と対話するような空間をつくりあげます。
その独特の建築観は、どこから生まれたのでしょうか?
本記事では、隈氏の実家とその周辺環境での原体験をもとに、彼の感性の源泉を探っていきます。
はじめての Audible なら 30日間の無料体験 を利用して、この本を聴けます
隈研吾が育ったのは「横浜と東京の間」、大倉山

隈氏は神奈川県横浜市の大倉山という住宅地で育ちました。
静かな住宅街でありながら、自然も残るエリアで、当時の暮らしには独特の空気感があったと語られています。
実家は木造平屋の住まいで、戦前の1942年に建てられたもの。
隈氏が小学校4年生のころには、すでに築20年以上が経過しており、著書『建築家になりたい君へ』の中でも「ぼろい家」と率直に表現しています。
この家は、もともと母方の祖父が畑仕事のために建てた小屋が原型でした。
そこに部屋を少しずつ増築して家族で住めるようにし、必要に応じて家をつくり変える文化が根づいていました。
家族で開かれた“設計会議”、発言は自由だった
隈氏の実家では、住まいの増築が必要になるたびに、家族全員で「設計会議」が開かれていました。
そこでは、子どもである隈氏も自由に意見を言うことができ、「空間は与えられるものではなく、話し合ってつくるものだ」という感覚を幼い頃から自然と身につけていきます。
さらに、家づくりの一部を自分たちで担うという方針も特徴的でした。
資金に余裕がなかったため、設計会議で決まった工事の内装仕上げは家族で担当するというスタイル。
費用を抑えるために「コスパがいい材料」を探し出し、工夫しながら空間を整えていくその体験が、隈氏の中に「素材を選び、使いこなす意識」を根づかせました。
この経験は、のちの建築作品においても生かされており、安価でありながら魅力的な素材を用いた設計に、今もその精神が息づいています。
厳格な父、明治生まれ──家族構成にも原点が
隈研吾氏が育ったのは、明治生まれで45歳年上の厳格な父、父より18歳年下の母、妹との4人家族でした。
父親は、家庭の中では圧倒的な存在感を持つ絶対的な家長でした。隈氏自身、「我が家においては独裁者のようだった」と振り返っており、男らしさや伝統を重んじる姿勢が、子ども時代の彼には少し息苦しく感じられたようです。
けれどもその一方で、建築やデザインに対して深い関心と知的好奇心を持つ人物でもありました。
職業は建築とは無関係でしたが、新しく東京に建つ建物を一緒に見に行きながら、隈少年に「これは誰が設計した建物なのか」と解説してくれることもありました。
そうした時間を通して、隈氏は「建築を見る目」「空間を読み解く視点」を父から学んでいったのです。
一方、母親はとても明るくおしゃれな人でした。
近所の方から「ファッション雑誌から抜け出たような素敵な方でした」と言われるような、凛とした存在感のある女性だったそうです。
家の中が父の好みでやや重くなりがちななかで、母は工夫を凝らしたインテリアや小物で、空間をやさしく彩っていました。
また、決して贅沢はせず、限られた家計の中で自分らしいセンスを表現することを大切にしていた母の姿から、隈氏は「美しさは生きるための力になる」ということを肌で学んだと語っています。
このように、対照的な両親の存在が、隈氏の感性や空間に対する考え方に強い影響を与えたのです。
実家の中と外、どちらも建築の原点

隈氏の原点は、家そのものだけでなく、その周辺での空間体験にも深く結びついています。
たとえば、家のすぐ裏にあった里山や竹林、防空壕跡の洞窟で日常的に遊んでいた隈氏は、音や光の違いによって空間が「まるで異世界のように感じられる」体験をしています。
緑に包まれる竹林、音がこもる洞窟──そうした空間の“質”を全身で感じていたのです。
さらに、公園脇の教会で体験した空間の劇的な変化──扉を開けた瞬間に広がる高い天井、ステンドグラスを通した赤や青の光に包まれる感覚──これが、建築というものの持つ力を初めて意識した瞬間だったと語られています。
まとめ|建築家・隈研吾にとって、実家とは
こうした体験があるからこそ、隈氏の建築には「素材と対話する姿勢」や「余白を生かす設計」が自然と表れます。
たとえば、那珂川町馬頭広重美術館や浅草文化観光センターなどでは、木の質感や光の繊細な取り込み方が印象的です。

それは、幼い頃に遊んだ竹林の光や、「ぼろい家」での手づくり空間、音の響き方まで感じた経験を、建築として再構成しているからなのかもしれません。
📘 隈研吾氏の原点をより深く知るには
『建築家になりたい君へ』では、こうした幼少期の体験がより詳しく描かれています。建築を志す人にとってだけでなく、「空間と生きる」感覚を知りたいすべての人におすすめの一冊です。
はじめての Audible なら 30日間の無料体験 を利用して、この本を聴けます