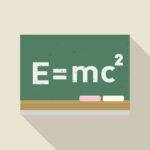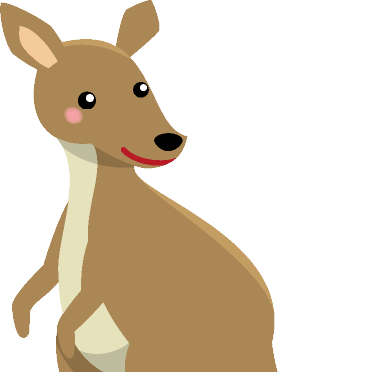はじめに
設備設計一級建築士試験は、設備設計の専門知識を問う高度な試験であり、合格するには過去問の徹底的な分析と理解が不可欠です。
本記事では、【令和6年度空調・換気設備】の過去問を詳しく解説し、解答のポイントや関連知識を整理しました。
過去問を効率的に学ぶことで、試験本番でも応用できる知識を身につけることができます。合格を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
令和6年度試験問題
過去問を確認することができます(講習実施情報→過去の考査問題等)
試験の概要などについてはこちらの記事も参考にしてください
-

-
【設備設計一級建築士試験の概要と対策】
2025/2/26
-

-
設備設計一級建築士 試験対策で必要なもの5選【おすすめアイテム】
2025/2/17
空調・換気設備 過去問解説
問1 冷却塔設備
冷却塔の法規については、頻出問題です。こちらの記事で詳しく解説しているので確認してみてください。
地上15階建ての屋上に設置→11以上であるため、構造が令第129条の2の6及び昭和40年建設省告示第3411号で定められている。
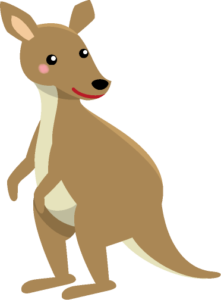
地上何階建てかの条件は見落としがちですが、11階未満の場合はこの告示が該当しないので、注意
- 充填剤:難燃性以外
- ケーシング:難燃材料
- その他主要部:準不燃材料
これらの条件から、冷却塔の設置間隔距離を確認
冷却塔(A)からほかの冷却塔(B)までの間は2m以上→3.0m≧2.0mのため、適切
冷却塔Bから屋内までは2.8m、窓がある場合は3m以上必要であるため、不適切
冷却塔についての基礎知識については、こちらの記事も参考にしてください。
問2 排煙設備
異種排煙方式となっている2部屋に対する問題
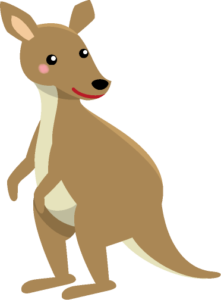
異種排煙、機械排煙、自然排煙、それぞれの規定を確認していきましょう
設問の図中の数値はすべてチェックしてきます
異種排煙方式の規定を確認
異種排煙方式となる間のガラリは天井高さの1/3以下のものに限る
図中でガラリの上端は床から900mmであるため、天井高さ1/3=933.3mm以内となっている
機械排煙の規定を確認
手動開放装置の高さは床面から80cm以上1.5m以下か
手動開放装置の上端が床面から1450
排煙機の能力は120m3/min以上かつ区画1㎡につき1㎥/min以上か
129㎡×1㎥/min×60(min/h)= 7,740 ㎥/h ≦ 7,750 ㎥/h
自然排煙の規定を確認
手動開放装置の高さは床面から80cm以上1.5m以下か
手動開放装置の上端が床面から1450
排煙口面積は、排煙区画床面積の1/50以上か
116㎡×/50= 2.32 ㎡ ≧ 2.3 ㎡
設問の2.3㎡だと排煙口面積不足のため、不適切
問3 火気使用室の換気設備
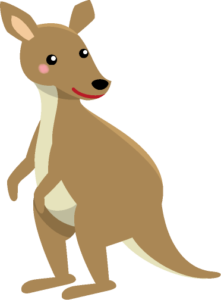
この問題は、見た瞬間すぐ答えがわかるように覚えておくべきことがあります
このポイントを押さえておけば、いったん回答し、他の問題に移ってから最後に戻ってきて計算も確認するという時間配分をとることができます
火気使用室の排気筒と厨房事務室からの排気筒が連結されているため、不適切
計算部分も確認してみます
火気使用室から排気フード付き排気塔+換気扇(排風機)のパターンです
排気フードは今回フードⅠ型となるので要求排気量V=30KQ
V=30KQ=30×0.93×50.5=1,408.95≒1,410 ㎥/h
厨房事務室からの風量50㎥/h を加えると、1,460 ㎥/h ≦ 1,500 ㎥/h(排風機風量)
問4 加圧防排煙方式
加圧防排煙は規定がたくさんあるため、設問に記載の文字、数字ですぐ判断がつくものからチェックしていく
手動開放装置
床面から上端が1,400≦1.5.m
空気逃がし口・空気逃がしダクト
空気逃がしダクトの材質について
・直接外気に接する
・厚さ1.5mm以上の鉄板及び厚さ25mm以上の金属以外の不燃材料かつ、常時開放されている排煙風道と直結
空気逃がし口の開口面積
Ap=(VH-Ve)/7
ここで、V=3.3√H=3.3√2.1 (隣接室が不燃材料の壁)≒4.78
Ap=(4.78×2.1-7200㎥/h/3600min/h)/7=1.148
図中空気逃がし口面積1.44≧1.148 → OK
圧力調整装置
乗降ロビーと隣接室の圧力調整装置の開口面積Admpを確認する
Admp=0.04VH=0.04×4.78×2.1≒0.40 ≦ 0.38(図中の圧力調整装置の開口面積)
※Vは空気逃がし口の開口面積算定時に出した風速
圧力調整装置の開口面積が必要面積以下となっているので、不適切
問5 設備関係規定 不適切箇所指示
選択肢A
住宅などの居室以外の居室
H15国交料告示第273号第4より
天井高さ6.9m未満は n=0.2
選択肢B
法35、令126の3第1項より
SDを設置することが望ましいとされている
選択肢
窓の開かない会議室(居室)は、機械換気が必要
V=20Af/N
N=一人当たりの占有面積(3を超えるときは3)
V=20×70/(70/30)=600
※Nが3を超えない場合、20×人数がVの値となる(1人あたり20㎥/h)
選択肢D
中央管理方式の室内環境で求められるのは、0.15mg/㎥
設問の0.16mg/㎥は規定値を超えているので不適切
おわりに
【令和6年度空調・換気設備】の過去問を解説しましたが、いかがでしたか?
過去問を繰り返し解くことで、法適合確認に必要な知識が確実に身につきます。
本ブログでは、他の過去問解説や設備設計一級建築士試験の対策情報も発信していますので、ぜひチェックしてください!
合格に向けて、一緒に頑張りましょう。
関連記事
過去問の出題傾向を把握するにはこちらをチェック